■週刊うちばや 第25刊 子供の時に好きだった本編
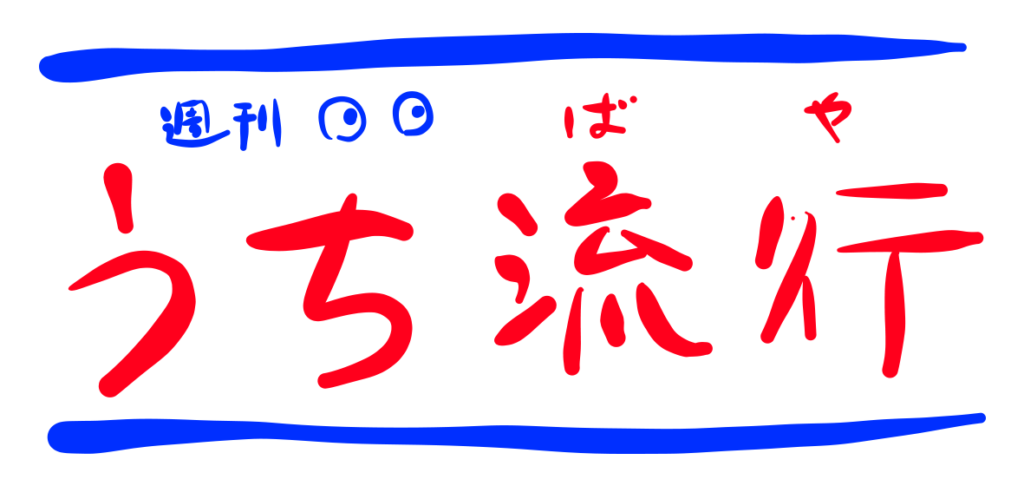
こんにちはAtaliです。
第25回になる週刊うちばや、今回のテーマは「子供の頃に好きだった本 編」です。
読書感想文は嫌いでも、何故か惹かれてしまった本はありませんか?
◆フォレストガンプ
![Amazon | フォレスト・ガンプ [DVD] | 映画](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61ar841ySyL._AC_SY445_.jpg)
フォレストガンプは映画版を元にした小説だったと思います。小学生がハマる本なのかと言われるとちょっと疑問符が付きそうなのですが、滅茶苦茶読みました。主人公の人生を一言で表すと波乱万丈。とにかく出会いと別れの繰り返しでストーリーが綴られています。その頃から色々な人に関わったりする憧れがあったのかもしれません。
そう思うと自分の人生も山あり谷ありですが、色々な人と一期一会を繰り返してきてる部分は、意外と悪くないストーリーを綴れているのかなと珍しく自己肯定してみたり。とにかくタフな主人公には未だに憧れがありますね。タフになりたいよタフに。
■ズッコケ三人組でいろいろと学びました
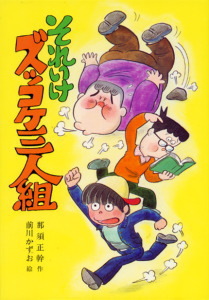
というわけで、子供の頃の僕の愛読書はズッコケ三人組です。
ハチベエ・ハカセ・モーちゃんの三人組が色んな事に巻き込まれてなんやかんやドタバタするシリーズなんですが、株式会社を作ったり特許を取るために発明したりとお前らほんまに小学生か?というくらい頭いいことばっかりしてます。面白くて学校の図書室でめっちゃ読みふけってたらいっときのあだ名がまんま『ハカセ』になったのもいい思い出。
この三人が中年になった後のお話もいろいろ出てるようなんですが、最初だけ読んで後は全く知らずのまま。いい機会なのでまた買ったり借りたりして読んでみてもいいかもしんない。
『子どもの頃に読んでいた本』について…

■まめかりの選んだテーマだが…
こどもの頃に読んだ本??あんまり覚えていなかった。
ただ、昭和の時代はやたらと○○全集とか○○図鑑シリーズとか
英語教材とか、科学と学習とか、訪問販売で売りつけられたような
シリーズ本が家に沢山あった。
田舎の人って(親の事)断りがいえないのだな。
小さい頃によくみていた本は、『世界の美術の本』と『魚図鑑』である。
世界の美術の本を何度も何度も繰り返しみていた。
====================================
※wikiからの引用以下
『アルノルフィーニ夫妻像』(アルノルフィーニふさいぞう (蘭: Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw、英: The Arnolfini Portrait))は、初期フランドル派の画家ヤン・ファン・エイクが1434年に描いた絵画。
====================================
この絵があまりにもリアルで子どもながら釘づけになった。
後ろの鏡に人が写っている。
美術書で外国の人をはじめてみるわけだが、日本の家屋とか洋服とか全く違うわけで。
自然にこういったものをみて みたこともない世界を覚えていくのである。
ヨーロッパのこの絵の印象が深く残っている。
じっと黙々とみていた。思い出すと こどもの頃の自分の横顔がみえる。
ルネサンスから現代美術まで、1冊にまとめられていた美術図鑑だった。
セザンヌ、ゴッホ、ダリやピカソの絵、マティスやクレーやシャガール。
美術の表現は自由だという事を自然に理解した。
最近では、漫画ちっくなダサい絵しか描いていないが、
18-22歳くらいまでは、現代美術にどっぷりつかり、
抽象的な版画作品やB1サイズの抽象画など作っていた。
人生の中で一番 渋い感性があった時代だった。
今はもう消えてなくなったよーん。
■魚の図鑑
『魚図鑑』のなかでは、鮫とマンボウとくじらのページを繰り返し見た。
ダイオウイカとマッコウクジラが戦っている絵も描いてあった。
鮫はのこぎりざめ、ハンマーヘッドなど、海の中にいるこの恐ろしい鮫たちの形が面白くて好きなページだった。
マンボウについては、絵をみるだけではどんな形をしているのか実際にわからなかったが、
なんにしても唐突すぎる形をしていたので本物がみたいと夢にみていた。
須磨か鳥羽水族館にいるのを知って、20歳頃 見に行った覚えがある。
肉厚のマンボウだが、平べったく、静かにおおらかに水槽のなかに浮いていた。
あまり機敏には動かない。やっぱり唐突ないきものだった。
浮いているだけだが、海の牛のようだと思った。
図鑑で夢にみていた通りの わけがわからない存在感だった。
マンボウとか サボテンとか肉厚の形状がすきだ。
そういわれれば、まめかりの青いキャラクターじたい
マンボウ起因のようにおもう。
いくつくらいから読書の記憶がありますか……。
保育園に通っているころは絵本を読んでたのかもしれないですけど、どんな本を読んでたかという記憶はないんですよね。
どちらかというと外でちゃんばらごっこなどをして遊ぶほうが好きだったので。
少年マガジンや少年サンデーの少年誌は買ってもらえなかったので漫画は友達の家で読んでました。
小学校に通いだしてからだと思うんですが、バスに乗って15分くらいのところにある商店街の小さな本屋で買ってもらった本がたぶん記憶にある好きな本というもの最初の出会いかなと思っています。
買ってもらったのは少年少女名作文学全集のようなものの中から「家なき子」と、世界の不思議というようなものを網羅した内容の本で、親としては外でばかり遊んでいるぼくにすこしは本を読むんでほしいと思っていたのかもしれません。
その買ってもらった「家なき子」を読んで泣いてしまった記憶があり、たぶん本を読んで泣いたのは記憶の中ではこれがはじめてだと思っています。
買ってもらったもう一冊のほう「世界の不思議」(仮称) もなかなかに面白い本で雑学好きはこの本の影響が大きいのではと思っています。
憶えている内容では、鉄砲魚という魚がいて葉っぱの上の虫を水鉄砲のように口から出した水で撃ち落とすだとか、カメレオンの体の色が環境の色にあわせて変えられるだとか、ピラミッドのことだとか、九州有明海の不知火現象のことだとかが書かれていたのでした。
いま思うとすごく寄せ集め感がありますけど読んだときは知らないことばかりですごく興味をもったのでした。
小学校の高学年のころになると、昆虫や植物や魚類の図鑑類が家に届くようになりました。
親が訪問販売で訪れたセールスから買ったと思うのですが、内容はカラー図版と詳細な説明が描かれたページが交互にあり、名前も学術名まで記載されている本格的なものでした。
よく見たのは、昆虫や魚などの生き物の図鑑で自分でつかまてきた虫や魚をこの図鑑で探して調べるということがすごく楽しいことだと気づいたのでした。
小学校のときには授業中に図書館で好きな本を読める読書の時間という授業があってここで多くの本に出会ったのでした。
小学校5年生の時に転校してきた友達のK君が借りていた恐竜図鑑を見てなんて面白そうな本が授業中に読めるんだろうと思ったものでした。
当時、ウルトラQやウルトラマンがテレビで放送されだしたころで、そのK君は絵がとてもうまくてなにも見ずにウルトラマンとか怪獣を描いてしまうのでクラスでも一目置かれている存在で、絵が好きだったぼくもその上手さに憧れていました。
その読書の時間で出会った本のひとつにSF小説があったのですが、たぶん小学生向けの本にSFというようなジャンルで分類されていたのかは記憶にありません。
H・G・ウェルズの「タイムマシン」「宇宙戦争」などの古典から、エリック・フランク・ラッセルの「見えない生物バイトン」といったものを読んだ記憶がありその後の読書の傾向はこの頃に培われたのではないかと思っています。
K君はいまはうちから電車で行ける距離に喫茶店を営んでいて、年に何度か彼の入れる美味しいコーヒーと手作りのケーキを食べてながら、とりとめのない話しをする付き合いが続いているのでした。
投稿者プロフィール

-
うちばや家のみんなが参加する、やや週刊 うち流行というコーナー。
各刊、4人の趣味嗜好を炙り出します。
あらためて、あんたそうやったーんと発見があれば面白いとおもうのだにゃ。(背後霊猫さん)
最新の投稿
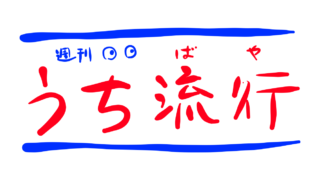 週刊うちばや2021-07-26■週刊うちばや 第70刊 好きなカレー 編
週刊うちばや2021-07-26■週刊うちばや 第70刊 好きなカレー 編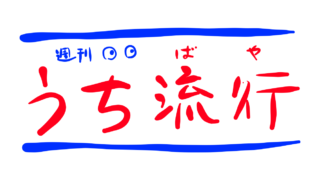 週刊うちばや2021-07-20■週刊うちばや 第69刊 涼しくなる話 編
週刊うちばや2021-07-20■週刊うちばや 第69刊 涼しくなる話 編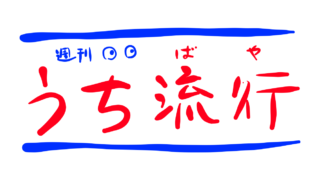 週刊うちばや2021-07-08■週刊うちばや 第68刊 最近みた印象に残っている夢は? 編
週刊うちばや2021-07-08■週刊うちばや 第68刊 最近みた印象に残っている夢は? 編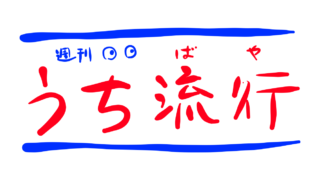 週刊うちばや2021-06-30■週刊うちばや 第67刊 タコ派? イカ派? 編
週刊うちばや2021-06-30■週刊うちばや 第67刊 タコ派? イカ派? 編
 (0) 記事が気に入ったら
(0) 記事が気に入ったら 