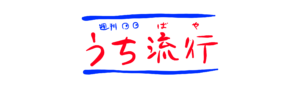■週刊うちばや 第6刊 こどものころの遊び編
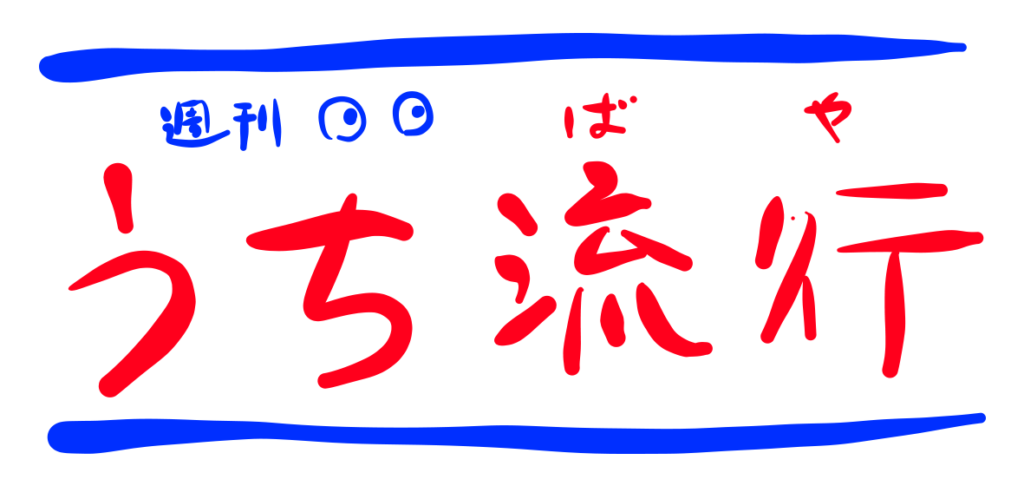
こんにちは、低気圧に絶賛やられ中のAtaliです。
第六回目となる週刊うち流行、今日のテーマは「こどもの頃の遊び」です。 この小さい頃っていうのはなんとなく小学6年生ぐらいまでの遊びをイメージ、全員なかなか被らないだろうなぁ。
■デジタルとアナログのハイブリッド
小さい頃の遊びについて思い出したときに、鬼ごっこ、缶蹴り、警ドロ、秘密基地づくり等のベタな遊びが思い浮かんだり、
レゴ、ミニ四駆、トランプ、UNO、遊戯王なんかのちょっと発展した遊びも大量に思い浮かんで、特別一つに拘って遊ぶ世代ではなかったのかなー?なんて印象を受けました。
また、その中でも僕らの世代を象徴するかもしれないなーという「プチデジタル」な遊びに「たまごっち」と「デジモン」があって、多分お値段的にも分かり易さ的にも「ゲームボーイ」を持たない家庭の子供にも広く普及していて、外で鬼ごっこなんかをして休憩にデジモン達を育てるというなかなか効率的な遊び方をしてた覚えがあります。
あと、これは特殊ケースの遊び紹介なんですが、うちばや家はGeee3の仕事と趣味の関係上一般家庭よりかなーり早くPCとインターネットの導入が行われていたんですね。
小さいころ親とどんな遊びをした?と聞かれて真っ先に思い浮かぶのが「Marathon」というコアなFPSゲームというのは日本全国でもそうとう希少な存在なのではないでしょうか。幼稚園児からPCゲームを楽しんでいたのはある意味で英才教育だったんだろうなぁ。おかげさまでタイピングの速さは社会人になってもずーっと役に立ってくれています。しかし最近は年なのかFPSをめっきり遊ばなくなってしまった・・・、Riotが公開予定の「VALORANT」が来たら老兵として参戦しなおしてみようかな・・・。
小さい頃のあそび
今週は、ちいさい時のあそびというテーマになった。
昭和世代のあそびなどかいてみたい。
■ロンパールームの着せ替えボード
小さいときのあそびだと、小学校や近所のこどもたちとの集団あそびなどいくつかある。
おにごっこ、はないちもんめ、警泥、ハンカチ落とし、
ぼうさんがへをこいた。
昭和世代には PCやゲームボーイなどなかったので、ひたすら外で遊んだ。
小学校の放課後の校庭遊びや、自宅に戻ると近所の少年たちが集まってあそぶ。
5歳4歳違いのふたりの兄がいたので、もっぱら、男子たちの中にごまめで入れてもらっていた。
足でまといになる部分があったんだろう。
兄がいない時は部屋でひとりあそびをしていた。
記憶にのこっているのは、着せ替え人形だ。
これは平面ボードに、女の子の絵がかいてある。
別にお洋服や帽子などのシールがあって それを張り替えて遊ぶという古典的なものだ。
何度も何度もくりかえし貼ってははがしするだけのあそびだ。
無の境地である。面白いとか笑うとか沸くとかないのだ。
箱庭療法てきなものなのかもしれない。
その頃は他にも紙系の着せ替えがたくさんあった。
とにかく、昭和レトロで時間の流れ方が今とは違うなと思う。
なかなかいい時代だったかもしれない。
現在も手帳にシールはりが好きな原点かもしれない。
写真をみつけた。懐かしい。まさにこれ。

■家族とのあそび
家族の団欒であそんでもらっていたゲームなど紹介したい。
人生ゲーム、ツイスター。
https://www.takaratomy.co.jp/products/twister/play/index.html
ツイスターは身体を使ったゲームで4色の●の書いたシートをひろげ、ルーレットで出た色に手や足を置いて倒れないようにするゲームだ。対戦するので相手の足や手にからんで倒れた方の負けである。
人生ゲームは、すごろくにお金の計算をいれたゲームで大富豪を目指すというものだ。
5人家族でするので家族団らん楽しかった。
家族でするゲームは、トランプ、百人一首(おもに坊主めくり)、囲碁の山崩し(音をたてたら負け)
シンプルだけど、家族で大笑いして楽しかった。
うちばや家は今でも『モノポリー』『クトゥルフ』(これは怖い怖い)
『点計算・役不明の麻雀』をしたりする。
89歳のおばあちゃんも麻雀をたしなむ。ばさまは 麻雀時はなんかいつもと違う気迫が漂ってくるので不思議だ。
みんな下手なので、牌がなくなるまで揃わないという事が多い。
自分の捨てた牌待ちとかもある。そんなレベルでも楽しいよ。
かつて『金持ちとうさんのキャッシュフローゲーム』などして遊んだりしたが、
何故うちばや家は経済を学べないのだろうか?
とにかく、日々のあそび心は大切だ。一杯遊ぼう~☆
■ポケモンカード、ミニ四駆、そんでからゲーム
僕が小学生の頃はたしかGBAからDSやPSPに移るくらいの世代で、ポケモンやらモンハンやらの通信プレイでにぎわっている頃でした。
僕は兄からけっこう影響を受けていたので、そんな流れに逆らうようにポケモンカードとミニ四駆というずれた世代のコンテンツにドハマりしていました。
ポケモンカードは今でこそ大流行していますが、当時はどっちかというと遊戯王やデュエルマスターズ辺りが流行っていた頃だったので一緒に遊べる友達は少なく、だいたい数人のいつものグループでデッキを交換しながら遊んでいた記憶があります。
あとは兄とずっと二人でデッキを回したり。こういう時に趣味が合う兄弟の利点というものを強く感じますね。今でもたまーにアナログとかデジタルのカードで対戦するくらいには趣味が合う。
ポケモンカードもミニ四駆も結構なハマり具合で、どれくらいかというと地方の公式大会に連れて行ってもらうくらいでした。
どちらも一回ずつしか出場経験はなく1-2回戦くらいで負けていたくらいの実力でしたが、想像以上に人が多くて滅茶苦茶テンションが上がっていたのは覚えています。
また、ポケモンカードの大会で強く覚えている出来事がありまして。
僕が試合に出ている間、連れ添いの兄と母はちょっと遠い所で待機しながら兄のデッキを確認していたのですが、その時に『世界大会に出たお兄さん(自称)』にデッキを組んでもらうという出来事があったようで。
「デッキはコンセプトを決めると組みやすいよ」とか、「メインで使うカードを絞って他でサポートする形がいいよ」とか、今考えるとカードゲームの基本的かつ真理的なアドバイスをもらいながら一つのデッキを完成させていて、試合から戻ってきた僕をめちゃくちゃびっくりさせました。
またそのデッキがめちゃくちゃ強くて、世界大会に出たよという普通なら信じにくい自称にも説得力が出ていたのです。
今思い出しても結構面白いエピソードだなーと思います。僕は直接会ったことないので顔も何も知らないのですが、どこかで元気にしているかなぁ。
そしてミニ四駆。
こちらは父にヤフオクなどで中古パーツを安く買ってもらったりして、好きなマシンを好きに組み上げるちょっと豪華な遊び方でした。
今から見ても結構なお値段のするベアリング系パーツ(1セット600円!)も中古パーツ詰め合わせセットなどに混ざっていたので、公式ルールで認められている6個のローラー全てをボールベアリングローラーにするという夢のようなマシンを作っていました。
また、たぶん非公式の物ですが安くて小さめのコースも買ってもらい、広めの部屋に組み上げて走らせることも可能でした。かなりいい環境で遊んでいましたね。
中古パーツの詰め合わせという事で、中にはこれ絶対公式のじゃないよなという怪しいパーツも紛れておりましたが、家のコースなら誰に怒られることもなく走らせることが出来ました。ただ、やっぱり非公式は質が悪いというかなんというか、「度を越えている」ようなパーツが多かったです。見た目が派手に怪しいモーターなんかは本当にものすごいスピードが出るため、1-2週するかしないかの内に派手にコースアウトしてしまい、次に走らせるときにはゆっくり周回しながら焦げ臭いにおいをまき散らすという何とも非公式っぽい挙動を見せてくれたりもしました。マシンが壊れなくてよかったよほんと。
あとはご多分に漏れずデジタルゲームで遊んでいましたね。この辺は今と変わらずという感じ。
基本的に携帯用ゲーム機は買わず、PS2などの家庭用ゲーム機で遊んでいました。
遊ぶものも割と兄の趣味が強く、無双シリーズや鬼武者シリーズなどの小学生にしてはちょっと渋めなゲームが多かった気がします。
また、当時は珍しくマイPC(父のおさがり)を持っていたので、小学校3年生くらいの頃からオンラインゲームを遊んでいました。
始めてすぐの頃はそりゃもういろいろとひどく、いわゆる「厨房」みたいな立ち回りのクソガキみたいな遊び方で楽しんでいましたが、その辺りも父や兄から指導・教育してもらい、1-2年経つ頃には無事に品行方正なネトゲプレイヤーに進化することが出来ました。当時は「ネチケット」という言葉が合言葉だったのを覚えています。
今でもネット上ではかなり行儀がいい方なんじゃないかなーと自負しています。リアルの方はわかんない!
バイクタクシーがなかなか捕まらないという夢を見ていて、遅くなりました。
すみません……。
漫画『20世紀少年』のはじまりは1973年、高校の放送室からT.Rexの20 センチュリー・ボーイをかけるところから始まります。
1970年は大阪万博が開催された年で、ぼくは14歳でした。
主人公のケンヂと同じ世代なので20世紀少年に出てくる遊びは、ぼくの子どもの頃の遊びと多くが重なります。
子ども時代の記憶というのは一体いつの頃までさかのぼって覚えているものでしょうか。
ぼくの場合はおそらく3歳くらいの記憶が断片的に思い出すもののうちではいちばん古い子どもの頃の記憶ではないかと思っています。
というのも、幼い頃に住んでいた家の近所に映画館があり、新作が映画館に入ってポスターが変わるとしばらくそれを眺めていた記憶があるのです。
その頃がだいたい3歳くらいのはずなのですね。
のちに両親から映画館のポスターが変わるとずっと見ていたという当時の話しを聞いて、たぶん記憶違いでもなさそうだと思っています。
そして両親と一緒に映画を観に行っていたということですが、暗い映画館の中でなぜかぼくはひとりでスクリーンを観ていたような記憶があり、それはきっと物語に夢中になっていたということなのかもしれませんね。
さて、そんな夢中にしてくれた映画とはなにかと言いますと、『月光仮面』だったり『新吾十番勝負』だったりするわけです。
いまの仮面ライダーがそうであるように、その主人公達が当時のぼくたちのヒーローでありました。
遊びも風呂敷をマントにして二丁拳銃を操る月光仮面役と怪人役であったり、そこらへんの野原から枯草の茎や棒切れを拾ってきて、葵新吾役と切られ役であったりを代わり番こにするというのがルールのような遊びをしていました。
ただ両親の話しによると、ぼくは切られ役をいつも希望していて、子どもというのはだいたいヒーロー役をやりたがるのに変わっていたようです。
そしてぼくの切られ役の演技はなかなか真に迫っていてうまかったということです。
そういうところで誉められてもなんだかなぁ、とは思いますが。
それからは父が建築関係の仕事をしていて、引越しをすることが多くなりあまり友だちと遊んだという記憶がないのです。
ある現場で訪れた地方では山を切り開いて高速道路を作るという工事を何年かしており、道路が出来るとその先に飯場という職人さんの住むところを移してまた道路を作っていくのでした。
父はその飯場の責任者のような立場であったようで、職人さんたちは何十畳もあるだだっ広いプレハブで雑魚寝をして生活をするのですが、ぼく達一家は離れのような部屋に住んでいて母が毎日、ご飯を炊いていた記憶があります。
そしてぼく達の部屋には唯一テレビが置いてあり、プロレス中継がある日は、部屋の中には飯場の職人さんでいっぱいで、入りきれない人は入り口からみんなでプロレスを観戦しているのでした。
その工事をしているうちに、そろそろ小学校に入る年齢になろうとしたころ、父は子どものために腰を落ち着けようと思ったらしく、それまで勤めていた会社を辞めてその近くの町のちいさな工務店に新しい職場を移したのでした。
いまではゼネコンと呼ばれている会社のひとつですので、子どものためによく決断したと思っています。
のちになんでこんな田舎を選んだのか、もう少し離れたところには商店街も銭湯もあったのにとも思ったのでしたが、いま思うと父の育った田舎とよく似ていることに気がつき、自分が育ったところとよくにたこの地で子どもを育てようと思ったのかもしれませんね。
もともとそこで育った地元の子どもでなく、幼稚園には行かなかったので小学校に入るまでは一人で遊ぶことが多かったです。
家の前が田んぼで、小さな用水用の溝があり、ヤゴやタガメや水カマキリなんかを飽きずに見てました。
昆虫もカエルも蛇もまわりにはたくさんいましたのでそういう生き物も遊びの対象でした。
小学校時代は、田舎で育ったので田んぼや野原でなにかしら遊びを見つけてましたね。
近くのお寺は境内に池があり、石橋が何箇所かに渡してあって菖蒲がとても綺麗なのですが、ザリガニがたくさん生息していて子ども達には絶好のザリガニ釣りの場所でした。
餌はなんでもよくて、スルメや竹輪なんかを糸に結んで垂らすとあっという間に引っ張ってきます。
子どもというのは残酷なところがあり、餌がなくなるとカエルやいま釣ったザリガニを餌にしてまた釣り始めたりするのでした。
小学校の夏休みの宿題は、何人もが昆虫採集をして提出していましたし、学校の近くの文房具店では夏休みになると昆虫採集セットなるものを売っていました。
昆虫採集も子ども達には学習というよりも遊びの延長のような自然と仲良くしていく機会のひとつであったのかもしれません。
漫画『20世紀少年』の中でケンヂたちが草むらに秘密基地を作るというのは、同じような環境が近くにあった子どもならけっこういるのではないかと思ったりしてます。
そのころの少年漫画にはなにかしらそういう秘密基地が登場して、少年たちをワクワクさせて真似させるような要素があるのでした。
そして生活しているまわりにはまだ子どもがそういう秘密基地もどきを作る場所があり、そういうところで遊んでいてもなにか言うおとなもいませんでしたしね。
そして銀玉鉄砲であったり、2B弾で武装して基地の争奪戦をやったりするわけですね。
2B弾とぼくらは呼んでたのですが、細長い直径5-6mm、長さ4-5cmくらいの筒に火薬が入っていて筒の先にはマッチ箱の側面ですると火がつくように細工がしてある花火です。
それをマッチ箱で擦ると白煙が出て、黄色い煙が出だすとけっこう大きな音で破裂するというものを駄菓子屋などで売っていましてみんなで投げ合いなどをしたり、蟻の穴に突っ込んで破壊したりして遊んでいました。
そういう環境で幼いころに遊ぶというのは、いまにして思えば何もないようで自然から滋味のようなものをもらっていたのかもしれないと、いまは感じます。
投稿者プロフィール

-
うちばや家のみんなが参加する、やや週刊 うち流行というコーナー。
各刊、4人の趣味嗜好を炙り出します。
あらためて、あんたそうやったーんと発見があれば面白いとおもうのだにゃ。(背後霊猫さん)
最新の投稿
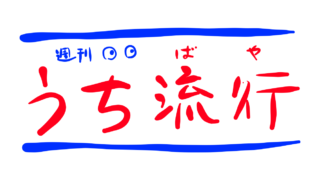 週刊うちばや2021-07-26■週刊うちばや 第70刊 好きなカレー 編
週刊うちばや2021-07-26■週刊うちばや 第70刊 好きなカレー 編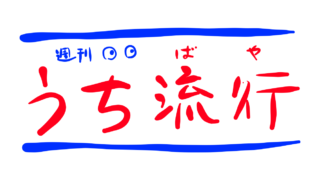 週刊うちばや2021-07-20■週刊うちばや 第69刊 涼しくなる話 編
週刊うちばや2021-07-20■週刊うちばや 第69刊 涼しくなる話 編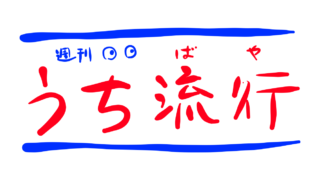 週刊うちばや2021-07-08■週刊うちばや 第68刊 最近みた印象に残っている夢は? 編
週刊うちばや2021-07-08■週刊うちばや 第68刊 最近みた印象に残っている夢は? 編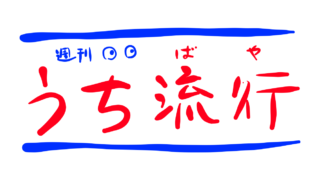 週刊うちばや2021-06-30■週刊うちばや 第67刊 タコ派? イカ派? 編
週刊うちばや2021-06-30■週刊うちばや 第67刊 タコ派? イカ派? 編
 (0) 記事が気に入ったら
(0) 記事が気に入ったら